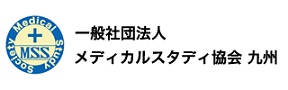開業医・クリニックの廃業率はどのくらい?廃業する3つの理由と今からできる対処法
こんにちは。
九州を中心に病院・クリニックのブランド構築・ホームページ制作を行う株式会社ディーエーエムです。
私たちも普段から数多くの先生方のご支援をしておりますが、毎年多くのクリニックが新規開業しています。
しかし、一方でクリニックの運営が立ちゆかなくなって、廃業となってしまうクリニックも一定数あります。
私たちはこれまで病院・クリニックだけに特化をして事業を行い、数多くの先生方とお話をする機会があったため、経験則から廃業するクリニックの特徴や傾向について共通点があることに気づきました。
本記事では、「クリニック廃業率と廃業する3つの理由、また廃業しないために今からできる対処法」について解説していきます。
>>クリニックのブランド構築に関して、無料ですぐに相談できます
開業医・クリニックの廃業率はどのくらい?

まずはじめに今回の結論から申し上げると、現在の開業医・クリニックの廃業率は約0.47%というデータがあります。
(参照: 帝国データバンク 「医療機関の休廃業・解散、倒産の 17 倍超(医療機関の休廃業・解散動向調査)」)
(参照: 帝国データバンク 「「診療所」の倒産、前年比 1.8 倍に急増(医療機関の倒産動向調査)」)
つまり、1,000軒のクリニックがあると仮定すると、年間約5軒のクリニックは廃業していることになります。
ちなみに一般企業の廃業(倒産)率は約1.4%です。
一般企業と比較すると、開業医・クリニックの廃業率はかなり低いですが、年々開業医・クリニックの廃業率は高くなっています。
開業医・クリニックが廃業する主な3つの理由は?
開業医・クリニックが廃業する理由としては、主に以下3つが挙げられます。
①院長の高齢化に伴い後継者がいない
②集患がうまくいかない
③地域での認知力不足
①院長の高齢化に伴い後継者がいない
まず廃業する理由として、院長先生の高齢化に伴い後継者がいないことが挙げられます。開業医・クリニックのドクターの年齢で最も多くを占めるのは60歳〜69歳の層です。
次に50歳〜59歳の層、70歳以上の層と続きます。
ドクターの約75%が上記3つの年齢層で構成されているため、開業医の高齢化とともに後継者が見つからず、そのままやむなく廃業するクリニックがかなり多いです。
②集患がうまくいかない
次に廃業する理由として、集患がうまくいかないことが挙げられます。ちなみにクリニックによっても異なりますが、1日の平均外来患者数は、一般的な医院の場合、「40人」が目安になります。
外部環境の大きな変化によって、集患がうまくいかないクリニックも多いです。
また競合他社(クリニック)が増えてきたことで、突然に集患がうまくいかなくなるケースも考えられます。
この場合、廃業というより、実質的には倒産の状態に近い形になります。
③地域での認知力不足
最後に廃業する理由として、地域での認知力不足が挙げられます。開業医がクリニックを構える地域で知られていないと、やはり集患・増患をすることは難しいです。
クリニックのブランド力やホームページでの宣伝がないと、時間が経つにつれて徐々に廃業(倒産)の道へと進んでいきます。
関連記事:【医療業界特化】福岡で病院・クリニックのホームページ制作なら、ディーエーエム(DAM)【開業医必見】
年々開業医・クリニックの廃業率は高まっています。

実は、、、開業医・クリニックの廃業率は年々増加傾向にあります。
実際に毎年開業医・クリニックの廃業件数は過去最多を更新しており、2022年は全国で約500軒の廃業が確認されています。
医療業界で働く私たちとしても、
「この状況をなんとかしないと!」
という想いで積極的な運営サポートをしています。
開業医・クリニックはなくならないと考えているようでしたら、改めてクリニックのブランド強化・戦略的なホームページでの宣伝について考えておく方が賢明と言えます。
>>クリニックのブランド構築に関して、無料ですぐに相談できます
開業医・クリニックが廃業しないために今からできる3つの対処法

開業医・クリニックが廃業しないためにできる施策としては、主に以下3つのことがあります。
①早期に後継者候補を見つける
②ブランディングを構築する
③マーケティングを強化する
①早期に後継者候補を見つける
たとえ患者満足度が高いクリニックであっても、開業医・ドクターが年を重ねて診療できなくなれば、一つの選択肢として、廃業することを検討しだすでしょう。もしクリニックを廃業させたくない、これからも事業を残したいとお考えなら、開業医・ドクターに子どもがいる場合は、早期に事業承継の話をしておきましょう。
また開業医・ドクターに子どもがいない場合は、M&Aなどを含めた第三者への承継を検討すべきです。
子どもが事業を承継してくれなかったり、M&Aに時間がかかることも想定されるため、万が一に備えて早めに準備を進めておくことを推奨します。
②ブランディングを構築する
前述の通り、一般的な企業と比較すると、開業医・クリニックの廃業率はかなり低いです。しかし、一方で毎年開業医・クリニックの廃業件数は過去最多を更新しています。
また年々新しいクリニックは生まれているため、これまで以上に開業医・クリニックの競争(外部)環境は激化しています。
患者様はホームページなどのプラットフォームを通じてクリニックを知りますので、今の時代は特にブランド力が弱いクリニックからは続々と患者様が離れていってしまいます。
ますます競争環境が厳しくなる医療業界で繁栄し続けるためにも、インターネット(オンライン)とリアル(オフライン)のブランディングを構築することが大切になります。
③マーケティングを強化する
上記のブランディング構築ができたら、あわせてマーケティングを強化することも大切になります。具体的には、
ホームページを通じて、
「どんなクリニックなのか」
「どんな医療サービスを提供しているのか」
「どんなドクター・スタッフが勤務しているのか」
を伝えたり、
SNSを通じて、潜在的な患者様に新しく来院いただいたりする必要があります。
マーケティング活動を通して、中長期的なファンを作っていかなければなりません。
関連記事:【開業医必見】患者さんが来ない主な3つの理由と今からできる対処法
【まとめ】クリニックを開業する前は、廃業するリスクを理解した上で準備を進めましょう!

今回は、「クリニック廃業率と廃業する3つの理由、また廃業しないために今からできる対処法」について解説してきました。
これから病院・クリニックの開業を検討中でしたら、またはすでに開業していて後継者や集患に困っているようでしたら、常に以下3つのことを意識しながら経営をしていくことを強く推奨いたします。
①早期に後継者候補を見つける
②ブランディングを構築する
③マーケティングを強化する
私たち株式会社ディーエーエムは、先生方とのコミュニケーションを大切にしており、病院・クリニックのブランド構築・ホームページ制作を通じたマーケティング強化のご支援をしています。
オンリーワンのブランド構築、またホームページを制作・運営し、長期間にわたって、病院・クリニックがより繁栄していくことを献身的にサポートいたします。
現在病院・クリニックの集患支援やホームページ制作を検討中でしたら、まずはお気軽にディーエーエム(DAM)にご相談ください。
株式会社ディーエーエムでは、病院・クリニックを経営する先生方のために、集患力を高める小冊子を無料配布しております。
スキマ時間で読みやすい12ページの冊子にまとめておりますので、ぜひ今のうちにお気軽にお申し込みください。
勤務医・開業医の違いを徹底解説! 年収や働き方の違いについても解説!
医師としてキャリアを積む上で、勤務医として働く道と、クリニックを開業する開業医としての道には、それぞれに特徴があります。
どちらを選ぶかで収入や働き方、さらにはライフスタイルまで大きく変わるため、自分に合った選択をすることが大切です。
本記事では、「勤務医・開業医の違い」や「年収や働き方の違い」について、さまざまな視点からわかりやすく解説していきます。
開業を考えている方に向けて注意点やアドバイスもお伝えしますので、ぜひ最後までお読みください。
勤務医・開業医の違いとは?

勤務医と開業医には、働き方や責任の範囲、収入面での大きな違いがあります。
勤務医は「雇用される医師として働く」
勤務医は病院やクリニックなどの医療機関に雇用され、医師として診療や治療に従事する形態です。
雇用契約に基づき、一定の勤務時間内で業務をこなします。
雇用先から給料が支払われ、給与体系は年齢や経験、勤務先の規模によって異なります。
医療行為に専念できる一方で、経営に関する負担はありません。
しかし勤務時間が長くなることや、夜勤や当直がある場合があるため、ライフワークバランスを保つのが難しいこともあります。
開業医は「自分でクリニック・病院を経営する」
開業医は自身でクリニックを運営し、医師としての診療だけでなく経営者としての役割も担います。
診療報酬から経費を差し引いた残りが収入となるため、患者数や診療内容、経費の管理が収入に大きく影響します。
自由度が高く、働く時間や診療スタイルを自分で決められる一方で、経営に関するリスクや責任も伴います。
特に開業初期は資金繰りや患者様数の確保が大きな課題となるため、医療技術だけでなく経営能力も求められます。
勤務医・開業医の年収の違い

勤務医と開業医では、収入の構造や安定性に大きな違いがあります。
「第23回医療経済実態調査報告」によると、勤務医の平均年収は1,461万円、開業医の平均年収は2,631万円となっています。
それでは、勤務医と開業医の年収の構造や安定性について、詳しく見ていきましょう。
【勤務医の年収】安定している
勤務医の年収は、病院やクリニックなどに雇用される形で支払われる給与が基本です。
給与は勤務先の規模や地域、診療科によって異なり、大都市の大規模病院では高い傾向があります。
役職が上がるにつれて収入が増える仕組みになっているため、経験を積むことで安定的に年収が上昇するのが特徴です。
一方、夜勤や当直の頻度が高い場合は手当が上乗せされる分、体力的な負担が大きくなることもあります。
【開業医の年収】経営次第で収入が変動する
開業医の年収は、診療報酬からクリニックの運営にかかる経費を差し引いた額が収入になります。
つまり患者様数や診療内容が直接収入に影響する仕組みです。
効率的な経営ができれば高収入を得ることも可能ですが、患者様数が伸び悩んだり、設備投資や人件費がかさんだりすると収入が減少するリスクもあります。
診療科や地域の特性によって需要が大きく異なるため、開業前の市場調査が重要です。
関連記事: クリニックのWEB集患(集客)は難しい?患者様に選ばれるためにできること!
勤務医・開業医の働き方の違い

勤務医と開業医では、日々の働き方や求められる役割に大きな違いがあります。
それぞれの働き方を詳しく見ていきましょう。
【勤務医の働き方】与えられた環境での業務
勤務医は病院やクリニックに雇用されて働くため、決められた勤務時間内で診療や治療を行います。
勤務時間は基本的に固定されていますが、夜勤や当直がある場合、長時間労働になることもあります。
職場の方針やルールに従って働くため、自分で決定権を持つ場面は少ないですが、業務が比較的安定している点は大きなメリットです。
【開業医の働き方】柔軟性と責任の両立
開業医は、診療スケジュールや働き方を自分で決められる自由があります。
例えば診療時間や休診日を調整しやすいため、家族との時間を優先することも可能です。
ただし自由な働き方の一方で、経営者としての役割を担う必要があり、経営状況や患者様数によっては長時間働くことも少なくありません。
さらに経営やスタッフ管理といった医師業務以外の責任があるため、スキルの幅広さが求められます。
勤務医が開業医になる際の注意点

勤務医から開業医を目指す場合、医療技術だけでなく経営や運営の視点が必要になります。
ここでは開業を成功させるために押さえておきたい重要なポイントを見ていきましょう。
【注意点1】計画的な開業準備をしよう
開業を成功させるには、しっかりとした準備が欠かせません。
まずは開業資金の確保が重要です。
開業には数千万円、場合によっては億単位の資金が必要となる場合が多く、銀行からの融資を受けることが一般的です。
この際に事業計画書を作成し、収支の見通しを具体的に示すことが求められます。
さらに開業地の選定は患者様数に直結するため、地域の人口や競合する医療機関の数や必要とされる診療科を考慮して選ぶ必要があります。
医療機器やクリニックの内装についても、自分の診療スタイルや予算に応じた計画を立てましょう。
【注意点2】経営スキルを身につける
開業医は医師であると同時に経営者でもあります。
そのためスタッフの採用や教育、患者数を増やすためのマーケティング活動、診療報酬や経費の管理といった業務が含まれます。
勤務医時代には触れることが少ないこれらの業務を学ぶために、経営セミナーや勉強会に参加するとよいでしょう。
税理士や経営コンサルタントといった専門家に相談し、支援を受けることで、負担を軽減しながら運営を安定させることができます。
【注意点3】患者様に信頼されるクリニックを目指す
開業医として成功するためには、地域の患者様に信頼される医療サービスを提供することが何よりも重要です。
例えば患者様目線に立った診療や丁寧な説明を心がけることで、患者様の満足度が向上し、口コミでの評判が広がりやすくなります。
診療以外の部分でも、ホームページの開設や予約システムの導入など、患者様が通いやすい仕組みを整えることが大切です。
関連記事: 【開業医必見】患者さんが来ない主な3つの理由と今からできる対処法
これから開業するご予定なら、患者様に選ばれるクリニックにしよう!

今回は「勤務医・開業医の違い」や「年収や働き方の違い」について解説しました。
勤務医と開業医には異なるメリットと課題があり、自分のキャリアやライフスタイルに合った選択をすることが大切です。
これからクリニック開業を検討中の先生方は、丁寧な診療や清潔な院内、わかりやすいホームページや予約システムを整えることで、地域に信頼されるクリニックを目指しましょう。
計画的に準備を進めて、患者様に選ばれる開業を成功させましょう。
クリニックのWEB集患(集客)は難しい?患者様に選ばれるためにできること!
こんにちは。
九州を中心に病院・クリニックのブランド構築・ホームページ制作を行う株式会社ディーエーエムです。
私たちは普段から数多くの先生方のご支援をさせて頂いておりますが、
初めてお会いした時には、
「WEBをどのように活用すれば良いのか分からない」
「WEBでの集患を自分で取り組むのは難しい」
というお話を多くの先生方からお聞きします。
確かにWEBと言っても、自院のホームページだけでなく、InstagramやLINEなどのSNSツールも複数あり何から手を付けて良いのか、どう進めていけば良いのか迷ってしまうのも無理はありません。
本記事では、まずは自院のホームページに的をしぼり、WEBでの集患が難しいと感じていらっしゃる先生へ向けて、患者様に選ばれるためにできることについて解説していきます。
>>株式会社ディーエーエムにWeb集患に関する無料相談をする
クリニックのWEB集患(集客)は難しい?

ホームページを持っていらっしゃる先生方でこのようなお悩みを感じていらっしゃる方はいませんでしょうか?
「ホームページは持っているけど、運用の効果を感じない。。」
「ホームページは持っているけど、ほったらかしになっていて活用できていない。。」
「WEBのことは難しくて良く分からないからできれば関わりたくない。でもどうにかしたい。。」
そんなお悩みを持っている先生は、まずはこのチェックポイントから手をつけてみることをおすすめします。
クリニックが患者様に選ばれるためにチェックしておきたい6つのこと
クリニックが患者様に選ばれるためにチェックしておきたいこととしては、主に以下の6つがあります。
①クリニックの独自性や強み、こだわりが分かりやすく掲載されているか
②診療時間や連絡先が見つけやすいところにありすぐに連絡ができるか
③どんな診療を行っていて、どんな問題を解決できるクリニックかが分かりやすく掲載されているか
④スマホで見やすいように最適化されているか
⑤院内の写真は明るく綺麗に撮れているか
⑥先生のプロフィールは充実しているか
まずはこれらをチェックしてみましょう。
①クリニックの独自性や強み、こだわりが分かりやすく掲載されているか
まずクリニックが患者様に選ばれるためにチェックしておきたいこととして、クリニックの独自性や強み、こだわりがわかりやすく掲載されているかがあります。クリニックの独自性や強み、こだわりとは、
・提供している診療へのこだわりポイント
・他のクリニックとの差別化ポイント
・クリニックの売り・強み
・クリニックが患者様に伝えておきたいこと
などがあります。
患者様からみても、上記項目が認識されないことには、まず「このクリニックに行ってみよう」というモチベーションに繋がりません。
そして、一度ホームページを訪れてくれたけど帰ってしまった患者様は、二度とホームページに戻ってきてくれない可能性もあります。
②診療時間や連絡先が見つけやすいところにありすぐに連絡ができるか
次にクリニックが患者様に選ばれるためにチェックしておきたいこととして、診療時間や連絡先が見つけやすいところにありすぐに連絡ができるかがあります。
患者様がホームページを訪れチェックすることとして
・診療時間内に受診できるか
・電話で相談や予約ができるか
などの情報になります。
特に現代人は少ない細切れの時間の中で大量の情報を処理していますので、すぐに連絡先などの情報が見つからないクリニックには不親切などのネガティブな印象を持ってしまいます。
③どんな診療を行っていて、どんな問題を解決できるクリニックかが分かりやすく掲載されているか
次にクリニックが患者様に選ばれるためにチェックしておきたいこととして、どんな診療を行っていて、どんな問題が解決できるクリニックかが分かりやすく掲載されているかがあります。先ほどの忙しい現代人のお話にも繋がりますが、忙しい中でホームページに訪れてくれた患者様は、一目でそのクリニックはどんな診療を行っていて、どんな問題を解決できるクリニックかが判断できないと離脱してしまいます。
クリニックで何が解決できるのかをホームページ上で分かりやすく訴求することが大切です。
④スマホで見やすいように最適化されているか
次にクリニックが患者様に選ばれるためにチェックしておきたいこととして、スマホで見やすいように最適化されているかがあります。令和4年度発行の総務省「情報通信白書」によると、WEBの検索などをスマホで利用する方は70%を超えています。
つまり大半の患者様は、スマホ経由でクリニックのホームページに辿り着くことになります。
スマホが普及している現代だからこそ、スマホで見やすいホームページの重要度が増してきています。
⑤院内の写真は明るく綺麗に撮れているか
次にクリニックが患者様に選ばれるためにチェックしておきたいこととして、院内の写真は明るく綺麗に撮れているかがあります。いくら実際の院内の雰囲気やインテリアが良かったとしても、ホームページ上の院内の写真が暗かったり画質が粗かったりすると、患者様にはその良さが伝わりません。
患者様が安心して快適に利用できるクリニックであることを訴求するためにも、院内の写真はこだわって撮影し選定する必要があります。
⑥先生のプロフィールは充実しているか
最後にクリニックが患者様に選ばれるためにチェックしておきたいこととして、先生のプロフィールは充実しているかがあります。患者様はクリニックを選ぶ一つの基準として、どういう先生が診察をしてくれるかということを気にしています。
・先生の経歴や得意領域
・先生の思いや熱意
など、他のクリニックと差別化を図るためにも、プロフィール欄は充実しておきましょう。
関連記事: 開業医・クリニックの廃業率はどのくらい?廃業する3つの理由と今からできる対処法
WEB集患(集客)ができないクリニックはどうなる?

WEBでの集患ができないクリニックは、将来的には経営状況が厳しくなっていく可能性があります。
ますますインターネットが普及する将来を考えると、WEBでの集患に積極的に取り組んだ場合とそうでない場合を比較したときにクリニックの経営状況は大きく変わっているかもしれません。
当社としては、
「クリニックの良さをもっと患者様に知ってもらいたい!」
「私たちが関わらせていただくクリニックにはずっと繁栄し続けてほしい!」
と常日頃考えております。
そのためにも
「ホームページだけでなくクリニックのブランド構築からお手伝いさせていただきたい!」
という想いで積極的な運営サポートをしています。
これからクリニックを開業される先生も、すでにクリニックを経営されている先生も、これから先、集患が難しくなる可能性があるという課題を少しでも感じているようでしたら、今のうちからクリニックのWEBでの集患に取り組まれることをおすすめします。
関連記事: 【開業医必見】患者さんが来ない主な3つの理由と今からできる対処法
【まとめ】患者様に選ばれるクリニックにしよう!

今回は、「クリニックのWEB集患は難しい?患者様に選ばれるためにできること!」について詳しく解説してきました。
現在集患がうまくいっているクリニックでも、中長期的な視点でみると、クリニックの経営状況がうまくいっているとは限りません。
これから新しいクリニックが開業し競合医院が増えていくことが考えられますので、今のうちからWEB集患対策をしておくことが大切です。
私たち株式会社ディーエーエムは、先生方とのコミュニケーションを大切にしており、病院・クリニックのブランド構築・ホームページ制作を通じたマーケティング強化のご支援をしています。
オンリーワンのブランド構築やホームページを制作・運営し、長期間にわたって、病院・クリニックがより繁栄していくことを献身的にサポートいたします。
現在、株式会社ディーエーエムでは、集患に不安を感じていらっしゃる先生方のためにWEBでの集患力を高める小冊子を無料で配布しております。
スキマ時間で読みやすい12ページの冊子にまとめておりますので、ぜひ今のうちにお気軽にお申し込みください。
【開業医必見】患者さんが来ない主な3つの理由と今からできる対処法
こんにちは。
九州を中心に病院・クリニックのブランド構築・ホームページ制作を行う株式会社ディーエーエムです。
私たちは普段から多くの開業医の先生方とお会いする機会がありますが、
「開業直後からクリニックに患者さんが来ない。。」
「開業準備を進めているけど、患者さんが来るか不安。。」
「なかなか患者さんが集まらなくて困っている。。」
「他のクリニックに患者さんが流れている気がする。。」
など直接先生方から悩みの声を聞くことがあります。
病院・クリニックに患者さんが来ない状態が続くと、いずれ経営が成り立たなくなるため、開業医としては早期にこの深刻な問題は解決すべきです。
本記事では、「【開業医必見】病院・クリニックに患者さんが来ない3つの理由と今からできる対処法」について解説していきます。
>>株式会社ディーエーエムに無料相談をする
【開業医必見】病院・クリニックに患者さんが来ない3つの理由

病院・クリニックに患者さんが来ない理由としては、主に以下3つが挙げられます。
①ホームページの情報が少ない
②エリアでの競争が激化している
③エリアでの認知が不足している
①ホームページの情報が少ない
まず病院・クリニックに患者さんが来ない理由として、ホームページの情報が少ないことが挙げられます。新規の患者さんのほとんどは、病院・クリニックに来院する前に病院・クリニックに関する情報収集をします。
そのため、そもそもホームページが存在しなかったり、ホームページに掲載している情報が少なかったり、古かったりすると、せっかくの新規見込の患者さんが離脱してしまいます。
患者さんが知りたい情報をホームページで用意できている病院・クリニックと用意できていない病院・クリニックでは、これからも続く情報化社会で雲泥の差をつけられてしまいます。
②エリアでの競争が激化している
次に病院・クリニックに患者さんが来ない理由として、エリアでの競争が激化していることが挙げられます。これまでうまく集患ができていたにもかかわらず、競合他社(病院・クリニック)が増えてきたことで、突然に集患がうまくいかなくなることはあります。
特に居住に人気なエリアですと、次々と競合他社が出てくるので、差別化ができていない病院・クリニックから集患が難しくなっていきます。
③エリアでの認知が不足している
最後に病院・クリニックに患者さんが来ない理由として、エリアでの認知が不足していることが挙げられます。病院・クリニックを開業したエリアで一定の認知をしてもらうことが集患・増患対策のスタートになります。
病院・クリニックのブランド力強化やホームページでの見せ方を工夫してエリアでの認知を獲得する必要があります。
患者さんは気に入った病院・クリニックに通い続ける

基本的に患者さんは自分が気に入った病院・クリニックに通い続けます。
実際にこれまでのあなた自身の通院履歴をさかのぼっても同じことが言えるのではないでしょうか。
「先生が親身に話を聞いてくれる」
「自宅から通いやすい」
「スタッフが優しく接してくれる」
「予約が取りやすい」
など、患者さんはさまざまな理由で自分が通う病院・クリニックを決めています。
そのため、まずはたくさんの患者さんが通ってくれる病院・クリニックになるためにも、病院・クリニックのブランド強化・戦略的なホームページでの宣伝は必要な条件になります。
患者さんが来ない病院・クリニックにしないために今からできる3つの対処法

患者さんが来ない病院・クリニックにしないためにできる施策としては、主に以下3つのことがあります。
①ブランドを構築する
②マーケティングを強化する
③リピーターの患者さんを増やす
①ブランドを構築する
年々新しいクリニックが開業しているため、これまで以上に病院・クリニックの競争(外部)環境は激化しています。患者さんはホームページなどのプラットフォームを通じてクリニックを知りますので、今の時代は特にブランド力が弱いクリニックからは続々と患者さんが離れていってしまいます。
ますます競争環境が厳しくなる医療業界で繁栄し続けるためにも、インターネット(オンライン)とリアル(オフライン)のブランディングを行うことが大切になります。
②マーケティングを強化する
上記のブランディングが実施できたら、あわせてマーケティングを強化することも大切になります。具体的には、ホームページを通じて、
「どんなクリニックなのか」
「どんな医療サービスを提供しているのか」
「どんなドクター・スタッフが勤務しているのか」
を伝えたり、SNSを通じて、潜在的な患者さんに新しく来院いただいたりする必要があります。
マーケティング活動を通して、中長期的なファンを作っていかなければなりません。
③リピーターの患者さんを増やす
ホームページの見栄えや病院・クリニックの外観がいくらよくても、先生方やスタッフの対応がよくなければ、患者さんが通院したいとは思ってくれません。そのため、中長期的に患者さんと良い関係を続けたいとお考えなら、患者さんが心の底から通いたいと感じるサービスの提供を心掛けましょう。
一人ひとりの患者さんと真摯に向き合えば、必ず良い評判・良い口コミが人伝で広がっていきます。
【まとめ】病院・クリニックに患者さんが来ない原因を把握できれば、これからの集患・増患はうまくいく!
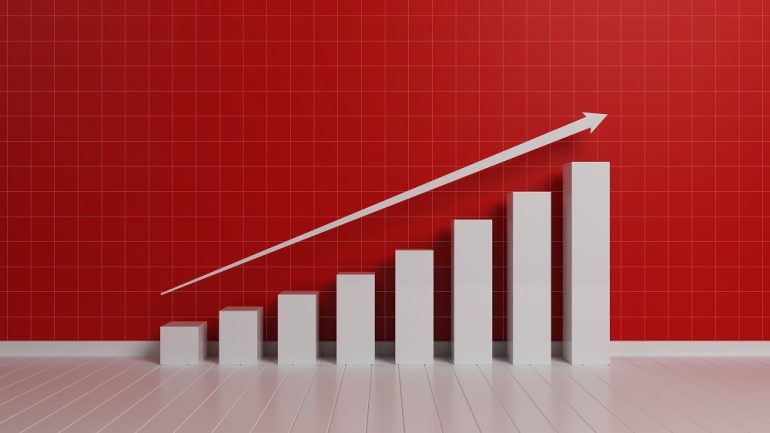
今回は、「【開業医必見】病院・クリニックに患者さんが来ない3つの理由と今からできる対処法」について解説してきました。
病院・クリニックに患者さんが来ないのには、主に以下3つの理由があります。
①ホームページの情報が少ない
②エリアでの競争が激化している
③エリアでの認知が不足している
私たち株式会社ディーエーエムは、先生方とのコミュニケーションを大切にしており、病院・クリニックのブランド構築・ホームページ制作を通じたマーケティング強化のご支援をしています。
オンリーワンのブランド構築、またホームページを制作・運営し、長期間にわたって、病院・クリニックがより繁栄していくことを献身的にサポートいたします。
現在病院・クリニックの集患支援やホームページ制作を検討中でしたら、まずはお気軽にディーエーエム(DAM)にご相談ください。
株式会社ディーエーエムでは、病院・クリニックを経営する先生方のために、毎月無料で最新のマーケティング情報をお届けしています。
最新のマーケティング知識を集患・増患に繋げたい方は、ぜひ今のうちからDAM TIMESにお申し込みください。